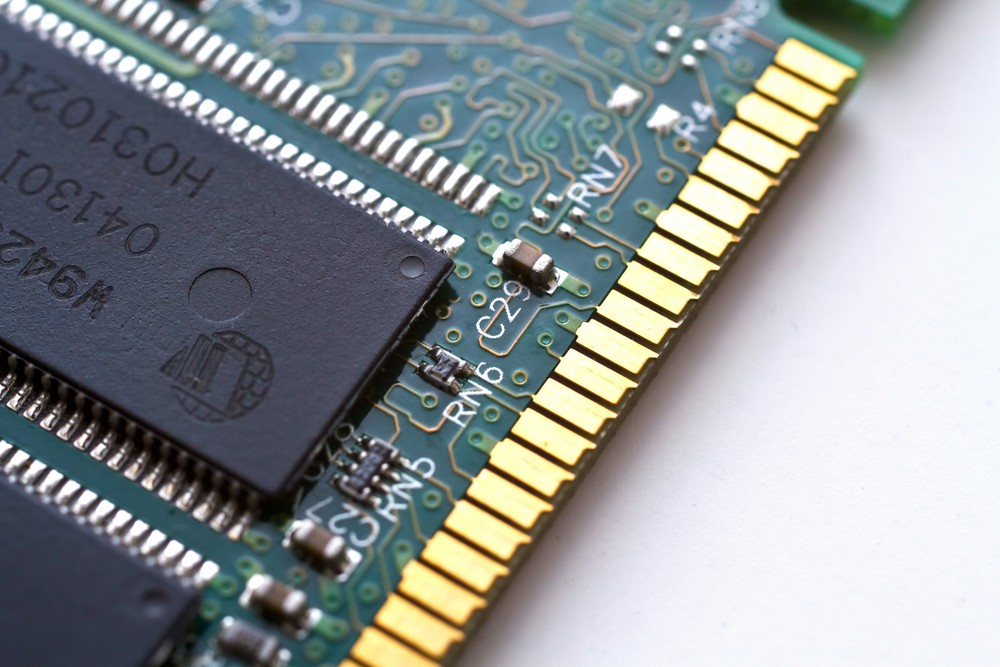医療過誤かも。でもどうやって争えば?
医療行為により又は期待された医療行為をしなかったことにより患者の身体、生命が侵害された場合を「医療事故」といいます。そして、この医療事故のうち医療機関側に過失がある場合を「医療過誤」といいます。
診断ミスや手術ミスなどがよくいわれるところでしょうか。
医療事故には他の事件と比べて特殊性があります。
ひとつは、独自の法律知識や医療知識が多分に要求されることです。
もうひとつは、医師には応召義務が課されていることです。応召義務とは、医師は診療を求められれればそれに応じる義務があるということです。つまり、医師は正当な理由なく診療を拒否した場合には損害賠償責任を負う場合もあるということであり、この傷病は診察や手術が難しいと思っても簡単には拒否できないのです。
このように医療過誤についての法律トラブルは他に比較して難しい分野、あるいは特殊な分野であるといわれます。
あなたが、医療過誤かも?と思ったとき、まずは弁護士に相談してみてください。医療過誤を取り扱っているような法律事務所は比較的少ないですが、インターネットなどで探してみるのがいいかと思います。医療過誤訴訟は、多額の費用と多大な労力を要する上に、前述のように法律知識や医療知識が要求される分野になります。これを既に医療過誤に遭われた方やそのご家族がご自身で手続を進めるのは非常に大変であると予想されます。
以下では、弁護士であればこのような流れで医療過誤事件を扱うということを簡単にですがみていきたいと思います。もちろん、ご自身ですることが不可能というわけではありません。
また、平成27年10月から医療事故調査制度という制度が新設されました。今後はこの制度を使って真相を究明することが期待されています。詳しくは、新しくできた医療事故調査制度で出来ることをご覧ください。
準備をしよう
まずは、時効によって請求権が消滅しないよう時効期間に注意して準備をしなければなりません。その上で、証拠資料を収集することになります。具体的には、カルテなどを収集することになるでしょう。このカルテは時効とは別に記録を保存しなければならない期間を経過すれば、なくなってしまう場合があるので注意が必要です。保険診療であれば3年が保存期間とされています(保健医療機関及び保険医療養担当規則9条)。ただし、3年経過しても保存されている場合もありますのですぐに諦めるべきではありません。
カルテなどの証拠を可能な限り集めたらどのような事件なのか事実関係を調査することになります。医師や家族など可能な限り聞き取りをする場合もあれば、カルテなどで調査することもあるでしょう。このような事実関係において本当に過失があったのか医療文献や法律文献を調査することになります。
このような証拠を集めるにはどうすればいいのでしょうか。
もちろん医療機関に依頼すればカルテ等を任意に開示してくれる場合があります。もっとも、カルテを開示する義務はありませんから、開示されない場合には、裁判所を通して確保することになります(証拠保全手続)。
交渉に入る
準備を終えて医療過誤が疑われる場合には、医療機関側と交渉することになります。
医療機関側も弁護士を付けて交渉の席につくことが通常ですから、通常は患者側弁護士と医師側弁護士で話し合いが行われることになります。ケースによってはここで解決となる場合もあります。
ADR(裁判外紛争解決手続)
医療過誤訴訟は結論の予測が困難です。できれば訴訟は最後の手段としておきたいというのが現状となります。そこで、たとえば、医療機関側も医療過誤の存在自体は認めているがその損害額について争いがあるなど、法律上の争いが少ない場合にはADRにより解決を図ることも考えられるでしょう。
具体的には、各所弁護士会が設置している紛争解決センターや裁判所の手続の一種である民事調停などが考えられるでしょう。ADRの特徴は、当事者のみでの話合いである交渉を、裁判所を除いた第三者を挟んで行うという点にあります。
訴訟提起(裁判)
医療水準は常にといえるほど発展しています。なので、いつの医療水準をベースにして医師に過失があったのかを判断すればいいのかという問題があります。この点については、「診療当時の臨床医学の実践における医療水準」を基準に医療行為に過誤があったかどうかが判定されるのが判例の傾向です。まあ、それはそうですよね。いくらいまの医療水準では過失があったと言える行為であっても、その当時の医療水準では防ぎようのなかった事故についてまで医師が責任を問われるのはおかしいからです。
とはいえ、この基準がじゃあ具体的にどんな感じで認定されているかといと、結構難しいのです。当然に医療過誤とわかるような場合には、表舞台に出てしまう裁判沙汰の前に交渉で解決することが多いでしょう。つまり、訴訟まで来るような医療過誤事件は医療過誤といえるかどうか本当に判断が付きづらいのです。もちろん訴訟中に和解が成立し解決する場合もありますが、判決にまで至れば医療現場に多大な影響を与えるようなケースもあります。これが医療過誤訴訟の特徴といえるでしょう。
実際に、医療過誤訴訟を提起した場合には、争点を整理する手続を経た上で、専門委員が選任されたり、鑑定手続が行われたりと、裁判所のみでは判断しづらい医療知識について裁判官も説明を受けながら審理がなされていきます。この審理を踏まえた上で裁判所が医療過誤があったのか、あったとしてどの程度の損害額なのかを認定し判決します。
何れにしても、医療事故が医療過誤といえるかについては慎重な判断が必要です。まずは弁護士に相談してみましょう。